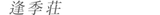能登方面 赤漆塗椀
能登半島地震の後に現地から出てきたと伝わる江戸時代の赤色漆の塗椀 深い赤みを持った塗椀は他産地では江戸時代の書写塗(第四形式)で類作がありますが 弁柄漆を用いたそれよりもやや一段と深い色味を呈した椀は能登・北陸の地からもその遺物が散見されます。 同地で制作されていた漆椀についての細やかな検証や系譜は未だ謎に包まれたままであります。 塗は堅く造られて侘びれた雰囲気椀縁に一箇所線疵が入ります。 ¥16000-(税・送料込)(※売上の内¥4000-を能登半島地震の支援金に充てさせていただきます。)寄付先:NPO法人ピーク・エイド:能登半島地震、支援 size: 直径 約13.5cm 高さ 約7.6cm 江戸時代(十八–十九世紀) 購入ご希望、詳細につきましては右下のチャットまたは各種DMからお気軽にお問い合わせ下さいませ。